SHINMOJI KININARINYO新門司キニナリーニョ
新門司キニナリーニョ 第1回
池西希スポーツダイレクター
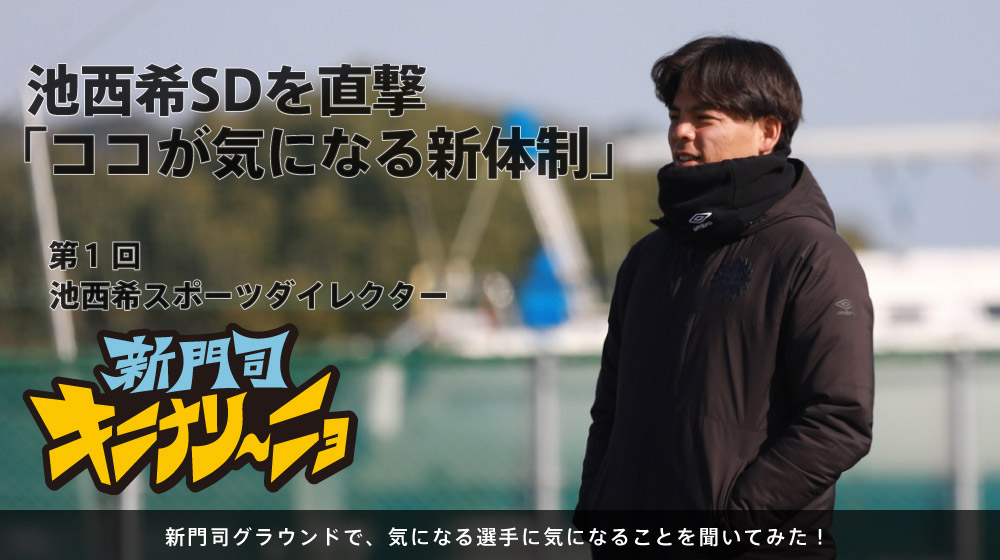
J3優勝とJ2昇格という高い目標を掲げて2025年シーズンに臨むギラヴァンツ北九州。今回は開幕直前企画として池西希スポーツダイレクターに今季の新体制について、いくつか気になる点を聞いてきました。
―まずは2年目の指揮となる増本浩平監督について。昨季7位という成績を考えると十分な働きをしたと考えて当然だと思いますが、改めて、強化部として昨季の増本監督の仕事をどのように評価しているのでしょうか?
主に4つの点で増本監督の働きぶりを高く評価しています。1つ目は、一昨年の最下位から去年は7位でフィニッシュと、単純に順位、成績を大きく上げてくれたこと。2つ目はチームとして良い人間関係を築きながら良い戦い方をしてくれたこと。3つ目は『ハイ・インテンシティ&ハイ・ポゼッション』というチームとして掲げたテーマに向かって1年を通してチャレンジし続けてくれたこと。そのテーマが昨年1年で十分に表現できたとは言えませんが、そこに向かう姿勢、意識のベースをしっかりとつくってくれたと考えています。それはきっと今年、来年と今後につながっていくもので、そうして『ハイ・インテンシティ&ハイ・ポゼッション』がわれわれの確固たるスタイルになるだろうと思っています。4つ目は、クラブの外に出ていろいろなイベントにも積極的に参加してくれて、クラブやチームを地域の方々にアピールしてくれたこともとてもありがたく感じています。
―今季の目標設定について。昨季はJ2昇格プレーオフに出場できる「6位以上」でした。結果的に7位に終わったので、今季も同様に「6位以上」という目標でもよかったのではないか、とも思うのですが?
昨年は終盤に勝点獲得に苦労して6位以上という目標を達成することはできませんでしたが、その達成が十分に可能と思える戦いをしてくれました。一昨季最下位のチームからしたら「6位以上」もかなり高い目標とも言えましたが、高い場所を目指すことで良い戦いをすることができた。そういうことを実際に経験したので今季は昨季以上の目標を設定し、そこにトライすることでチームはさらに成長、進化できるのではないかと考えて『J3優勝&J2昇格』という目標を掲げることにしました。
―昨年末には新体制が固まっていました。チーム構成が固まる順番は普通、上位カテゴリーのJ1、次がJ2最後にJ3となると思うのですが、補強を含めて迅速な新体制作りができた理由は?
まずは、昨年一緒に戦ってくれたスタッフ、選手とまた一緒に戦いたいとの思いがあり、彼らがその思いに早い段階で応えてくれたことがベースとしてあります。その上で、新戦力獲得に向けた動きを早くから行ったことも理由だと思います。われわれ強化部が意識したのは獲得に向けた決断を早く、思い切りよくすること。素早く決断して動くことを意識した時に「あと少し待てば良かった……」と後悔することもあるとは思います。しかし、決断を躊躇している間に欲しいと思っていた選手を他チームに取られてしまうこともあります。どちらが納得できるかと考えた時の答えが、思い切って決断することでした。もちろん素早く思い切りよく決断するためには、そのための判断材料が必要になります。前の所属チーム、それはアカデミー時代、育成年代の時の事も含めた情報をなるべくたくさん集める。そうして判断の精度を上げる。その努力は、強化部スタッフの池元友樹を含めてしているつもりです。
―選手が「早い段階でのオファーにクラブの熱意を感じた」と口にすることはよくあることですから、素早い決断とオファーは選手獲得に有効だと言えるのでしょうね
はい、有効だと考えています。特にJ3というカテゴリーのチームにおいて、まずはこちらから早く想いを伝えることが何よりも大事だと思っています。
―「早い段階で移籍を決断してくれる選手」とは、例えば所属先のチームで十分な出場機会を手にできていない選手とか?
そうです。J1やJ2の中で、高い能力を持っているけれどもチーム事情や年齢による経験不足、またはケガによって出場機会が限られている選手たちですね。そういう選手たちは「早く試合に出て活躍したい」、「そうすることで自分を成長させたい」との強い意欲と覚悟を持っています。そうして加わってくれた選手は、新シーズンに向けての準備も早くからできるし、それによって合流後にスムーズにチームに溶け込み、シーズン序盤から良いパフォーマンスを見せてくれるとも考えています。しかし今回、早い段階でチーム体制を整えられたのは、こちらからのオファーに対して早い段階で答えをだしてくれたスタッフや選手のおかげですね。
―新加入のうち、育成型も含めて期限付き移籍で獲得した選手が多いですよね。期限付き移籍の多くは1シーズンの契約なので、次年度には元のクラブに帰る可能性が高いということ。もちろん財政面で余裕があるクラブが少ないJ3リーグでは、この傾向は強いのでしょう。しかしそういう選手たちで戦うことが果たして次年度以降の戦いにつながるのか、またはクラブの財産となるのか。そういう疑問も生まれます。
良い選手を完全移籍で獲得するには、例えば所属元のクラブとの契約が残っていれば移籍違約金を含めてかなりの費用がかかります。それに対して期限付き移籍の場合は費用を抑えることができます。そういう現実がある中で、今年われわれはJ3優勝とJ2昇格という目標を掲げました。それを達成するためには、やはり戦力レベルを上げることが必要で、そのための手段として期限付き移籍による補強がメインとなったということです。そして、そういう補強のやり方で来年につながるのかという疑問に対してですが、私たちは少し異なる視点から「継続性や再現性がある」と考えています。
―どういうことでしょうか?
昨季主軸として活躍してくれた期限付き移籍の選手たちの多くは、今季チームを離れることになりましたが、彼らの活躍ぶりはほかのチーム強化部も目にしているので、「ギラヴァンツ北九州に預ければ若い選手は良い経験を積み、成長できる」という考えを持ってくれることになります。期限付き移籍にて獲得してきた選手たちが試合に出場をし、活躍をすることで『若手育成の場』というクラブとしての一つのブランディングにつながっているということ。それを継続していけば、毎年のように有能な選手、若手が出てきている日本のサッカー事情を考えれば、1年間だけは終わらない、再現性のある戦力補強、チームづくりができると考えられます。『人は変われどもチーム力は向上する』、そういうことです。
―新戦力にはベテラン選手も含まれます。それは昨季の課題であるゲーム運び、特にきっちり試合を締めるといった部分での働きを期待してのものなのでしょうか。
星広太と町田也真人が『ベテラン』にあたるのだと思いますが、もちろん試合運びの面で彼らが経験を生かしてうまくコントロールしてくれるとは思います。しかし、単純に高い目標を達成するため、昨シーズンの課題に対する貢献度やチーム力向上という視点からオファーをかけた選手が、たまたまベテランだった、ということ。確かに去年よりもチームの平均年齢は1歳ほど上がりましたが、年齢、経験による働きだけを期待しての獲得ではありません。
―昨年はアカデミー出身である坪郷来紀選手がシーズン途中から地域リーグを戦う『ベルガロッソいわみ』へ育成型期限付き移籍の武者修行に出し、今季は官澤琉汰選手も同クラブへ育成型期限付き移籍。その狙いは?
まず若い選手は公式戦で出場経験を積むことがとても大事だと考えています。地域リーグとはいえ、レベルは低くはありません。それは練習試合をする中で実際に感じるところでもあります。そういう中で、しかもJクラブから来ているということでの期待を背負ってプレーすることは彼らが成長する上でかなりのプラス材料になると考えています。
―1月の新体制会見でアカデミーの強化にも力を入れたいとお話しされていました。
アカデミーの責任者も兼ねている自分としては、まず組織としてどういう形のものを目指すかを明確にし、それをスタッフみんなとしっかり共有することが、アカデミー組織の強化、有能な選手の育成という『成功』への第一歩だと考えています。そのために今年から3年を掛けてトライするステップを明確化してスタート地点に立ったところです。
―いまの時点で「ここが足りない」と考える点は?
現在、U-18が福岡県リーグ1部に所属、U-15が昨季の九州リーグから降格して今年は福岡県リーグを戦う状況にあります。もちろん九州リーグを戦いたいという思いが当然のようにある中で、ハード面を含めた環境、指導者と選手の質が著しく物足りないとは思っていません。つまり何かが大きく不足しているわけではないけれども、ブレイクスルーするための何かが足りない。そんなふうに感じています。
―ブレイクスルーにつながるアカデミー組織としての熱量を高めたい、そのための明確な目標設定でもあるということですね。
トップチームが優勝を目指すためにはやはり組織としてのエネルギーアップが不可欠です。同様にアカデミーも組織として3年後の明確な目標を掲げることで、そこに対しての共通言語が生まれ、それによってエネルギーが高まっていくのは間違いのないこと。それと同時に結果が伴えば、成長に向けての良いサイクルが生まれる。特にアカデミーに関しては、その好サイクルを生み出すことが非常に大事だと考えています。私は過去にV・ファーレン長崎でアカデミー組織に属していましたが、厳しい戦いを勝ち抜いて全国大会出場を果たし、高いレベルの戦いを経験することで組織としての意識は高まり、それによって有能な選手や良い指導者が集まりやすくなりました。それが私の言う『好循環』です。そこから当然、我慢強い取り組みが必要になりますが、そういうサイクル誕生を間近に見た経験もあるので、いま、自分がアカデミーの責任者という立場になってそういう好循環を何とかして生みだしたい、そのためのシステム構築を進めたいと強く思っています。
[取材・構成:島田 徹]
新門司キニナリーニョ Archive
新門司キニナリーニョ2024 Archive
